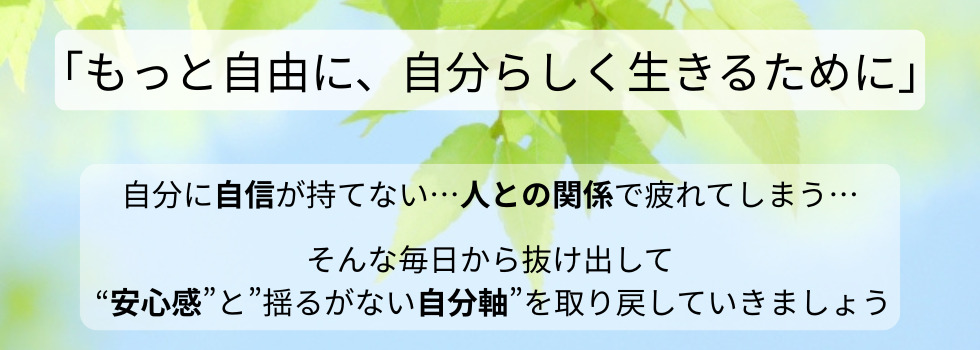不安障害かも?|“ただの心配性”では片づけられない不安の正体
心配性だとよく言われるけれど、最近はちょっと違う気がする。
理由もなく強い不安に襲われたり、胸が苦しくなったり……。
「このままじゃまずいかも」と思いながらも、誰にも相談できずに悩んでいませんか?
この記事では、そんなあなたのために、「不安障害かもしれない」と感じる方が知っておきたい心のしくみや、対処のヒントをお伝えします。
「不安障害かも」と感じたときに考えたいこと
不安障害とは、日常生活に支障をきたすほど強い不安や心配が続く状態のこと。
とはいえ、最初は「ただの心配性かな」と思ってしまう方がほとんどです。
たとえば、
- いつも最悪のシナリオばかり想像してしまう
- 他人にどう思われているかが気になって仕方ない
- 不安で外出や人と会うのが怖くなる
- 体に異常がないのに、動悸・息苦しさ・めまいがある
こうした不安が強く続いている場合、「気のせい」や「性格のせい」ではなく、心の奥にある原因を見直すタイミングかもしれません。
心配性と不安障害の違いとは?
「心配性」は、何か起きたときに備えようとする傾向です。
一方「不安障害」は、不安が生活に大きな影響を及ぼしていたり、本人のコントロールを超えてしまうような状態。
心配性は日常の範囲で機能することもありますが、不安障害の場合、
- 不安で眠れない・食べられない
- 常に緊張していて、リラックスできない
- 理由がわからないまま不安が続く
など、生活の質が著しく下がってしまうことも。
「おかしいな」と感じたら、それは心のサインかもしれません。
不安の正体は“心の奥の記憶”かもしれない
理由がはっきりしないのに、不安になる。
それは、過去の経験や環境で身につけた「思い込み」や「心の癖」が関係していることがあります。
たとえば、
- 子どもの頃から「ちゃんとしなきゃ」と育ってきた
- 親が不安定で、安心感のない環境だった
- 何か失敗すると怒られる家庭だった
こうした過去の体験が、心の深い部分に「不安を感じやすい状態」を作っていることがあるのです。
そのため、表面的な対処だけでは根本的に楽になるのが難しく、心の奥にある“無意識の設定”を見直すことが必要な場合もあります。
「気のせい」とは言わないでいい
周りの人に相談しても、「考えすぎじゃない?」と言われてしまう。
でも、あなたが感じている不安は、決して気のせいではありません。
理由がわからない不安ほど、本人にはとてもつらいものです。
だからこそ、あなたの感覚を否定せず、丁寧に向き合っていくことが大切です。
一人で抱えないで|心の専門家と一緒に整理しよう
不安が強すぎて、日常生活に支障が出ている。
安心したいのに、いつも緊張している。
そんなときは、ぜひ専門家のサポートを受けてみてください。
カウンセリングでは、不安の背景にある「思考のクセ」や「過去の体験」を整理し、心を落ち着ける方法を一緒に見つけていきます。
不安は、無理に消そうとしなくてもいい。
ただ、“安心できる心の土台”を、少しずつ整えていけばいいのです。
不安を抱えるあなたへ|まずは一歩、踏み出してみませんか
不安を感じやすいのは、あなたが繊細で、感受性が豊かだからかもしれません。
でもそのまま放っておくと、心も体もどんどん疲れてしまいます。
あなたが本来の自分らしさを取り戻すために。
まずは、心の声に耳を傾けてみることから始めてみてくださいね。
▼ カウンセリング / コーチング
不安の根本を見つめ直し、“安心できる自分”を取り戻したい方へ
▼ 関連する人気講座
- 自分軸講座:不安に振り回されない“自分軸”をつくる心の基礎トレーニング
> 講座の詳細はこちら